- 国際NGOプラン・インターナショナル 寄付・募金で世界の女の子を支援
- NEWS一覧
- 【開催報告】子ども支援フォーラム in 熊本(5/28・熊本市)
【開催報告】子ども支援フォーラム in 熊本(5/28・熊本市)
イベント
(更新)
2016年4月14日の夜以降、震度7や6強を観測する地震が相次いだ熊本県。震災体験と余震によるストレス、不安に戸惑う子どもや保護者たちへのサポートの必要性が指摘されています。熊本緊急支援を行なっているプランは、東日本大震災以来連携している有志の心理士グループ、ケア宮城と5月28日に熊本市内で子ども支援フォーラムを開催し、子どもたちや保護者が震災を乗り越えていくうえで有益な支援の手法や心構えについて4名の登壇者が会場からの質問も交えて話しました。
話題提供者として、山形大学教授で臨床心理士の上山眞知子氏(ケア宮城役員)、兵庫県立光風病院、兵庫県臨床心理士会理事の中谷恭子氏、尚絅大学短期大学部教授で日本学校心理士会熊本支部支部長の緒方宏明氏が登壇。プランからは東日本大震災で支援活動を行った膳三絵職員が加わりました。
心理的な配慮をこめた日常生活を
上山氏は、世界保健機関(WHO)などの国際支援のガイドラインと、そのガイドラインに基づいて行われる心理社会的支援の有効性について東日本大震災での具体例を紹介しました。さらに、ガイドラインで指摘されているデブリーフィング(語らせること)の問題点を説明し、それに替わる支援の具体例として、避難所における子どもの遊び場の有効性を挙げました。こうした日常生活に心理社会的支援を溶け込ませる工夫が求められることの大切さを指摘しました。

上山眞知子 山形大学教授
国際的な基準にそった支援事例の紹介
膳は、国際NGOとして支援の国際基準から導き出される支援の事例をテーマに話しました。1.安心感、2.ポジティブ感、3.自己効力感、4.連帯感、5.希望という5つの要素が込められた支援プログラムの事例を東日本大震災支援の例を参考に紹介しました。

膳三絵 プラン・ジャパン
震災後の子どもの問題行動はむしろ健康的
阪神淡路大震災を体験した中谷氏は、震災後に子どもたちが親たちに気遣って無理に我慢して、頑張っていたことに言及。いわゆる「良い子」こそ、何年も後に症状を出す場合もあり心配されるところで、震災の恐怖体験をした子どもたちの間で震災後に問題行動が出るのはむしろ健康的である点を指摘しました。
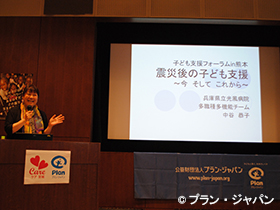
中谷恭子 兵庫県臨床心理士会理事
心理士同士の連携による学校と保護者への支援の必要性
地元熊本で災害直後から心のケア支援にあたっている緒方氏は、2016年4月14日から5月27日までに1577回にものぼる地震が発生していることに触れ、長引く避難生活も相まって子どもたちや保護者の間でストレスが募っている現状を分析しました。県内の学校心理士会と臨床心理士会が連携して、保育や学校現場への支援、保護者への講話や面接、保育者養成校との連携による子どもたちとの遊び、絵本の読み聞かせ、歌などの活動の必要性を説きました。

緒方宏明 尚絅大学短期大学教授
会場との質疑応答では、東日本大震災で両親を亡くした沿岸部の子どもが、内心は対応の仕方に戸惑っていた担任の教師から毎日「お前大丈夫か。へそ出して寝てるんじゃねーど」と親が発する言葉のように声をかけられたことが日常のペースを取り戻す大きな支えになっていたことなど、阪神淡路、東日本大震災での体験から出た心理的ケアのポイントがわかりやすい言葉で話し合われました。
東日本大震災のときに有志の心理士と行政、プランが連携して教員支援を行なった事例から、熊本においても似たような連携体制で子ども、保護者、教員の支援ニーズに応えていこうとする意見が多くだされました。

実体験にもとづく話に共感が寄せられました

内容の濃い質疑応答となりました
あなたの寄付で、誰かの人生に可能性が生まれる。
公式SNS
世界の子どもたちの今を発信中







参加者の声