- 国際NGOプラン・インターナショナル 寄付・募金で世界の女の子を支援
- プラン・ブログ
- 「New World,New Rules~新型コロナウイルスとともに生きる」後編
「New World,New Rules~新型コロナウイルスとともに生きる」後編
理事長
池上 清子

理事長ブログ
(更新)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を受けられている皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。厳しい状況のなかで、現在、大変多くの皆さまに、プラン・インターナショナルの「新型コロナウイルス対策緊急支援」へご寄付をお寄せいただいておりますこと、まずはお礼申し上げます。
遠い国の女の子に寄り添う支援
これまでの感染症の流行と同様に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにおいても、社会の不平等や格差、脆弱性などが浮き彫りになっています。そのような中、プランは、特に見過ごされがちな女の子や女性の問題に力を入れて取り組んでいます。
途上国では、保健衛生に関する啓発活動、手洗い指導、生理用品の配布、医療従事者(女性)に対するハラスメントからの保護、ホットラインやシェルターの設置による女の子や女性たちのジェンダーに基づく暴力からの保護などの活動を行っています。

プランが配付したリーフレットを読むインドネシアの女の子

ザンビアでの手洗いトレーニング
プランが運営しているヨルダンの難民キャンプのコミュニティ・センターには、多くの女の子や女性たちが通っていましたが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のため、現在は一時閉鎖しています。そのような中、プランは、難民の人々にマスクやその他の保護具を作るためのキットを配付し、携帯電話を使った遠隔操作で作り方指導も行っています。こうした取り組みは、難民の女性たちの孤立防止につながるとともに、外に出られないストレスの発散にもなっています。

ヨルダンでプランが配付した手作りマスクキット

ヨルダンのシリア難民キャンプの子どもたちと
日本国内におけるプランの取り組み
プランは、日本国内においても、さまざまな取り組みを展開しています。
「女の子のためのチャット相談」の開始
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を受けた若年層の女性を対象に、社会福祉士の資格を持つプランの職員によるチャット相談を開始、適切な保護を受けられずにいる若い女性たちに寄り添った支援を実施しています。
- ※2022年12月2日(金)より、「女の子のためのチャット相談」は、プラン・インターナショナルが運営する「わたカフェ」サイトに移設しました
日本の若い女性に与える影響について独自調査(アンケート)を実施
4月に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が若い女性に及ぼしている影響について緊急アンケートを実施しました。15~29歳の女性364人からの回答分析から、「女性である」ことで、家事・育児の負担増加、経済的な影響への不安、DVや性暴力被害への不安を抱えていることが、明らかになりました。プランは、アンケートで明らかになった課題に基づき、日本政府に対して5月12日、対策についての要望書を提出しました。
オンライン報告会の開催
支援者の皆さまやプランの活動に関心をお寄せくださっている方たちを対象に、活動国の日本人駐在員によるオンライン報告会を開催しています。
5月24日には、アフリカにチャイルドを持つスポンサー向け「オンラインサロン」が開催されました(アフリカのザンビアにチャイルドを持つ私も一般参加者でした)。ウガンダの駐在員による、ウガンダに逃れた南スーダン難民が居住する地区での活動紹介がありました。プランは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策として、簡易手洗い場の設置と石けんの提供、難民のリーダーが予防・衛生メッセージを拡散するためのメガホンの配布などを実施しています。実際に現地で活動をしてきた駐在員の言葉には重みがありました。その他の活動国においてプランが行っている新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策については、以下のページでご紹介しています。ぜひご覧になってください。
分岐点にいる私たち
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の大流行は、保健・医療・衛生面の危機をもたらしているだけでなく、政治、経済、社会、文化、国際関係などすべての分野に影響を及ぼしています。第2波や第3波の襲来、それを含めて世界的な危機を乗り越えられたとしても、私たちのこれからの生活や社会は根本的に異なるものとなり、今までと同じような形に戻ることは無いと思います。
今の段階では、ポスト新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が、どのような世界になるかはわかりませんが、私たちはこれからの社会をどのようなものにしたいのかを考える必要があります。今、世界中の人々は、新たな秩序のもと、新しい社会を作る(New World, New Rules)分岐点にいるのではないでしょうか。
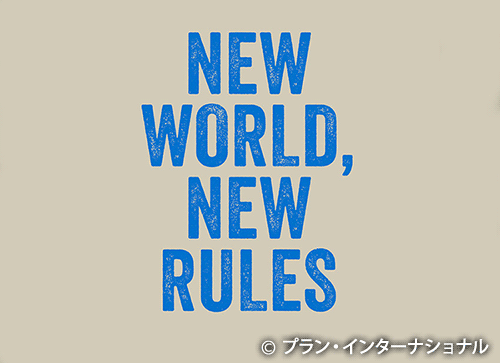
SDGsが目指す社会の実現にむけて
プランの災害対策責任者コリン・ロジャースは、「もっともリスクが高いのは難民や紛争の影響を受けている人たちです。プランは、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大防止を重要な使命として、影響や被害を受けやすい人たちに支援を届けるため、さまざまな対策を講じなくてはなりません」と述べています。この考え方は、持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)」と相通じるものがあります。災害、感染症の大流行、紛争、などでは、通常の開発をすすめるときよりも、さらに「誰一人取り残さない」取り組みが必要です。また、緊急支援が終わったあとも、「誰一人取り残されない社会」を構築することが重要です。パンデミックや災害、復興、開発のそれぞれの段階で、女の子や女性たちを含むもっとも弱い立場に置かれた人々に焦点をあてて活動するプランの姿勢が変わることはないでしょう。
2016年12月7日にインドネシアのアチェ州でマグニチュード6.5の地震とそれに伴う津波が発生したときに、「ビルド・バック・ベター(Build back better)」※がスローガンになったことを思い出します。
このときに言われた‘Better’が何を指すのか、その中身が問題です。今回分かったことの一つに、「これからの世界は、ヒトとウイルスの共存の模索をせざるを得ない」ということがあります。「感染症には国境がない」という頭でわかっていたことを、体でも理解したという現状に鑑みると、今こそ、世界中の人々が国を越えて手を取り合い協働していかなければなりません。世界中の誰もが自分らしく生きられる社会を構築していくことを目指し、団結することが求められているのです。
そのような中、プランは、支援者の皆さまと途上国の現場をより密接につなぐ一方で、女の子や女性たちなど現地に暮らす人々の声に耳を傾け、ニーズを正確に把握して支援に結び付けることを果たすべき役割として、自分たちにできることを一つずつ着実に実行していきたいと考えています。
- ※「よりよい復興」(ビルド・バック・ベター)とは、災害の発生後の復興段階において、次の災害発生に備えて、より災害に対して強靱な地域づくりを行うという考え方
最後になりましたが、皆さまからいただきました「新型コロナウイルス対策緊急支援」への貴重なご寄付は、現地のニーズに即した有意義な活動に大切に使わせていただきます。引き続きのご支援、何卒よろしくお願い申し上げます。
あなたの寄付で、誰かの人生に可能性が生まれる。
公式SNS
世界の子どもたちの今を発信中






