- 国際NGOプラン・インターナショナル 寄付・募金で世界の女の子を支援
- プラン・ブログ
- 「国際ガールズ・デー」にむけユースと奮闘した半年
「国際ガールズ・デー」にむけユースと奮闘した半年
アドボカシーチーム
澤柳 孝浩

日本
(更新)
アドボカシーチームの澤柳です。私が所属しているアドボカシーチームは、女の子や若い女性が直面している国内外のジェンダー課題の実態を明らかにして、その状況を改善するために関係各所に働きかけを行っています。なかでも、私はユースアドボカシー(ユースとともにすすめる提言活動)の担当として、日常的にプラン・ユースグループのメンバーと議論を深めながら活動しています。
ユースも参加した『世界ガールズ・レポート2020』
毎年10月11日の「国際ガールズ・デー」は、その設立を国連に働きかけたプラン・インターナショナルにとって、世界へメッセージを発信する重要な日です。毎年国際ガールズ・デーに合わせて『世界ガールズ・レポート』を発行しており、2020年のテーマはオンライン・ハラスメントでした。
日本ではユースグループが中心となって、女の子や女性が受ける「オンライン・ハラスメント」に関するインタビューやグループ・ディスカッション調査を実施。調査結果をもとにレポートを完成させました。
そして、「国際ガールズ・デー」を目前にした10月9日、ユースによるオンライン・ハラスメントの調査をもとにして一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構※との意見交換会も実施することができました。
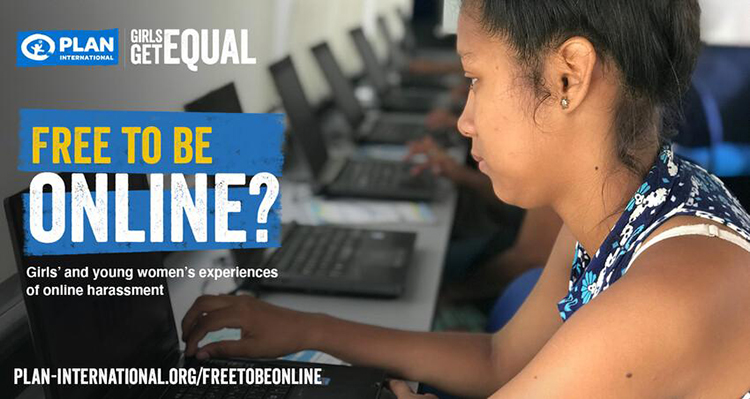
「女の子にオンライン上の自由を」をテーマに調査
- ※ Byte Dance株式会社、Facebook Japan株式会社、LINE株式会社、Twitter Japan株式会社を中心とした、日本初のソーシャルネットワーキングサービス(SNS)事業者と有識者から構成される組織。SNS上の課題解決に取り組んでいる。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響
プラン・ユースグループは、例年春に新メンバーを募集していますが、今年は面接もオンラインで行い、5月からの活動も手探りの状態で開始しました。私が本格的にユースアドボカシーを担当してから2年になりますが、これまでとはまったく違う方法ですすめていくことになり、当初は非常に困惑しました。
例年は合宿などで長時間をともに過ごし、相互理解を深め、お互いに率直な意見交換をできる信頼関係を築きあげていきますが、今年は対面でのコミュニケーションをすることができません。ユースアドボカシーでもっとも大切な要素はチームビルディングで、その良し悪しに活動の質がかかっていると思いますが、率直な意見を交わす場をつくるための時間がかかっていると感じています。特に今年度入ったメンバーはユースグループとしての帰属意識を得るのも難しく、本人たちの苦労も多かったのではと思っています。
一方、オンラインのミーティングツールは、どんなに離れていてもつながることができるというメリットもあります。地方からの参加が容易になったり、都合が合わずこれまでミーティングに参加できていなかったメンバーも、オンライン化により参加する機会が増えたのはよい傾向です。

オンラインツールでミーティング
事務局の役割は自主性を後押しすること
「ユースアドボカシー」のすすめ方はさまざまな方法がありますが、プランでは、ユースとスタッフが協力しあって活動しています。また、日本国内での独自の活動を行うだけではなく、プランが世界的に設定したテーマにも積極的に参加・協力すべきだと考えています。これまでテーマの選定に関わる機会が少なかった点は、今後活動として強化していきたい部分です。
今後2021年の6月にかけて、これまでの活動の学びを生かし、ユースメンバーが独自に設定するテーマに沿ってアドボカシーを行っていく予定です。メディアによる報道、外部団体との連携など、少しずつではありますが、プラン・ユースグループの活動が結実し始めていることを感じています。
自分が若かったころを振り返ると、周りの大人たちを驚かせるようなことを企みたいといつも思っていました。だからこそ、ユースメンバーには、若いエネルギーを使ってオリジナリティのある活動をしてもらいたいと考えています。どうぞユースメンバーの活動への応援をよろしくお願いします!
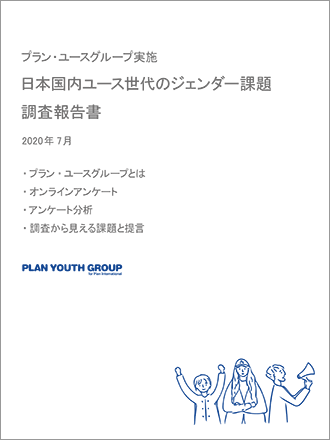
プラン・ユースグループ実施 日本国内ユース世代のジェンダー課題 調査報告書
昨年度の調査報告書 テーマはユース自らが設定しました
関連リンク
あなたの寄付で、誰かの人生に可能性が生まれる。
公式SNS
世界の子どもたちの今を発信中







新たに活動に参加したプラン・ユース 勝田さん(大学4年生)のコメント
ジェンダー課題についてディスカッションするユースメンバーたち(2019年)
「5月からプラン・ユースとして活動に参加しています。オンライン・ハラスメントの活動はもちろん、ほかのメンバーとの交流がとても楽しくてやりがいを感じています。ジェンダーに関心がある同世代の仲間たちと出会い、毎日たくさんのことを語り合えるようになったからです!
『三人寄れば文殊の知恵』というように、仲間がいれば社会変革のために大きな一歩を踏み出せるのではないかと勇気づけられています」