- 国際NGOプラン・インターナショナル 寄付・募金で世界の女の子を支援
- 特集
- 貧困に苦しむ人々の生活とは?現状の暮らしから必要な支援を考える
貧困に苦しむ人々の生活とは?現状の暮らしから必要な支援を考える
貧困は、現在世界中が直面している最も差し迫った問題のひとつです。世界中で数十億人もの人々が、十分な食料や飲み水、教育、医療を受けられないなど命の危険にさらされています。途上国の課題と捉えられがちな貧困問題は、日本を含む先進国においても深刻化しています。
SDGs(持続可能な開発目標)の目標1で掲げられている「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」ために、世界の貧困問題についての理解を深め、解決策を探ってみましょう。

干ばつによる貧困(ニジェール)
もくじ
世界の貧困問題の現状
現在、世界中の7億6700万人、10人に1人が極度の貧困状態(1日当たり1.90米ドル以下の生活)にあると言われています。貧困は、人々からさまざまな機会を奪い、社会的排除の原因となります。
また、子どもの生きる権利、成長し発達する権利、教育を受ける権利、家庭的環境で養育される権利といった子どもの権利条約で保障されている権利を侵害し、子どもたちの健やかな成長の妨げとなってしまいます。
2020年10月に世界銀行とユニセフが発表した調査分析によると、新型コロナウイルス感染症パンデミック以前に極度の貧困状態に置かれていた子どもたちは、全世界で6人に1人、およそ3億5600万人※1
に上ると推定されています。
最低限の栄養、衣類、住まいのニーズが満たされていない状態を指す極度の貧困を表す国際基準「1日1.90米ドル未満」※2で生活する子どもの3分の2をサハラ以南アフリカが、5分の1近くを南アジア地域が占めています。2018年時点では、サハラ以南アフリカの3億4200万人、南アジアの2億人が極度の貧困状態に置かれていました。※3

過酷な生活を強いられている難民の親子(エチオピア)
最新の発表で、世界人口は2022年11月に80億人に達したことが判明しました。急激な人口増加の背景には世界の衛生状況の改善や乳幼児死亡率の低下などプラスの局面がある一方で、貧困、飢餓、栄養不良といった課題が増幅し、保健サービスや教育の普及を難しくすることが危惧されています。世界銀行は、極度に貧しいとされる人口を、2022年の貧困率8.51%から試算し、およそ6億8500万人に上ると発表しました。そのため、国際社会には、これらの人々を誰1人取り残すことなく助け、貧困の連鎖を断ち切る取り組みを展開することが求められています。
- ※1「Global Estimate of Children in Monetary Poverty: An Update - World」(Relief Web)
- ※2 国際貧困ラインは2022年9月に2.15米ドルに見直されました
「極度の貧困人口、コロナ禍で7000万人増 世銀試算」(日本経済新聞) - ※3「世界の貧困層の半数は子ども」(United Nations Development Programme)
- 出典:「1年を振り返って:14の図表で見る2019年」(世界銀行)
世界にある深刻な貧困問題と生活の例
グローバル化による負の影響を受けている地域や人々のことをグローバルサウスと言い、グローバル化の恩恵を受け経済的な発展を遂げている先進国をグローバルノースと呼んでいます。2000年以降、長らくグローバルサウスで浮き彫りになっていた環境問題や人権問題などがグローバルノースにおいても顕著となり貧困も加速化しています。
ここ日本においても、厚生労働省が2018年に発表した「平成30年国民生活基礎調査」(PDF版)※にて、子どもの貧困率(17歳以下)は13.5%で、約7人に1人の子どもが貧困状態にあることが明らかになっています。本調査によると、2018(平成30)年の貧困線(等価可処分所得の中央値の半分)は127万円となっており、「相対的貧困率」(貧困線に満たない世帯員の割合)は15.4%となっています。

ハイチでは貧困のために治療が受けられず5歳未満の死亡率が高い
子どもたちの貧困問題
上述の国民生活基礎調査によると、世帯主が18歳以上65歳未満の「子どもがいる現役世帯」の世帯員の「子どもの貧困率」は12.6%であるのに対し、「大人が1人」のひとり親世帯では48.1%と約半数が貧困状態にあることが分かっています。また、ひとり親家庭の親の就業率は、母子家庭の母親、父子家庭の父親ともに全世帯(15歳~64歳の就業率)と比べて高い傾向にあるものの、正規雇用の割合は、父親が67.2%であるのに対し母親は39.4%と、シングルマザーの場合にはより収入が少なく養育費の捻出も難しい状態にあることが明らかになっています。OECD(経済協力開発機構)の最新調査では、コスタリカの貧困率が20.3%と加盟38カ国のうち一番高い数値を示しているものの、日本の「ひとり親」の相対的貧困率はこれ以上に高い状態にあることが分かっています。
世界に目を転じてみると、健康、教育、生活水準の面における貧困の程度と発生頻度を明らかにするものとして、国連開発計画が2010年の人間開発報告書において導入した多次元貧困指数(Multidimensional Poverty Index)※1
があります。2018年の推計では、貧困のなかで暮らす人々の半数が18歳未満の子どもであることが明らかになっています。
低・中所得国を中心に104カ国で6億6200万人の子どもが健康、教育、生活水準などの側面において貧困に陥っている※2
のです。この数値からも分かるように、世界には、十分な食事を取れずに健康状態が悪く、満足に教育を受けられない子どもたちが多く存在しています。

山岳地帯に住む少数民族(ベトナム)
- ※1「第2章 2.2.2 国連開発計画「多次元貧困指数(MPI: Multidimensional Poverty Index)」(内閣府)
- ※2「世界の貧困層の半数は子ども」(United Nations Development Programme)
地域別の貧困問題
サハラ以南のアフリカ
アフリカ大陸のサハラ砂漠より南に位置するサハラ以南アフリカと呼ばれる地域は、過去に類を見ないほどの深刻な貧困問題に直面しています。サハラ以南のアフリカ諸国の大半(48カ国中33カ国)は後発開発途上国(LDC:Least Developed Country)であり、人口の約半分が1日約1.90米ドル未満の生活を送っています。この地域には、内戦や紛争、難民、干ばつによる飢餓、HIVとエイズをはじめとする感染症のまん延など、発展を阻害する深刻な問題を抱える国が多く、国際社会からの多大な援助を必要としています。
サハラ以南に位置する国の一つウガンダでは、2020年から2022年までの3年にわたり食料と家畜の生産量が平均を下回っている状況が続いており、気候変動や災害、風土病や治安の悪化などが複雑に絡み合い、広範囲で食料危機を引き起こしています。

少ない食事を分けあう家族(ウガンダ)
出典:「ウガンダ:2023年4月~8月の深刻な食糧不安状況と2023年9月~2024年2月の予測」(IPC - 統合食料安全保障段階分類)
南アジア
南アジア地域は、過去数年間の急成長に伴って貧困が減少し、保健や教育の面で大きな進歩が見られました。その一方で、1日1.90米ドル未満で生活している人の割合については、2015年の段階で世界の貧困層の3分の1に相当する約2億1600万人だった数値が、新型コロナウイルス感染症がもたらした危機により、世界最大規模で増加することが推測されています。
国連人口基金(United Nations Fund for Population Activities:UNFPA)による最新の推計で世界最多の人口14億2860万人を有するとされているインドでは、貧困層に属する人口が1億7000万人以上で、その割合は世界の貧困層の約4分の1に相当します。このように人口の約3割を貧困層が占めているインドの貧困を削減することは、全世界の貧困削減を目指すうえで重要なカギとなります。
インドは、1990年代から順調な経済成長が続いているものの、所得分配が不平等なままであることと人口増加が著しいことから、特に農業就業者や都市部の低所得層、低カースト層が依然深刻な貧困に直面しています。インフラ整備が経済成長に追いついていないことも大きな問題となっています。電力や水の供給が不足しているほか、道路、鉄道、航空の交通インフラも輸送量の増大に対応しきれなくなっていることは、産業の発展にとって大きな障害となるだけでなく、人口流入によって膨張する都市部の生活基盤を悪化させる理由になっています。また、インドでは全国的にSDGs(持続可能な開発目標)達成にむけても、栄養、保健、ジェンダー等の社会開発面で多くの課題を抱えています。

児童婚の廃止を訴える女の子(インド)
【出典】
「インド」(外務省)
「インド|海外での取り組み」(JICA)
「経済的貧困にある子どもたちの世界的な推計:最新情報」(世界銀行)
貧困撲滅のための取り組み
世界の指導者はSDGsを採択するにあたり国際アジェンダのトップに貧困削減の問題を据えました。特に、目標1では、極度の貧困も含め、いかなる形態の貧困も終わらせ、平和と繁栄を確保する普遍的な行動を求めています。そのため、貧困の原因となる広範な要因に対処できるよう各国政府や市民社会組織の能力強化が急がれています。
国連の取り組み
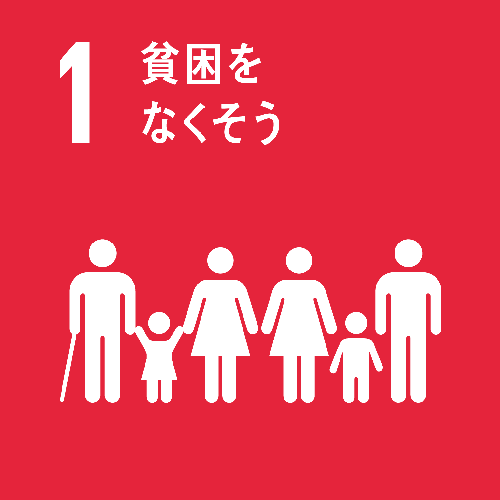
SDGsの目標1「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」ことを達成させるために世界ではいくつもの取り組みがなされています。
貧困の削減を主要な優先事項としている国連開発計画(United Nations Development Programme: UNDP)は、食料安全保障を強化すること、雇用の機会を創出すること、人々が土地や融資、技術、訓練、市場にアクセスできるようにすること、住居や基本サービスの提供を改善すること、そして人々が自分たちの生活を形成する政治に参加できるようにすることなど貧困の原因となる広範な要因に対処できるように政府や市民社会組織の能力強化に努めています。
また、飢餓や栄養不良、貧困のない世界、食料と農業が持続可能な方法ですべての人々の生活水準の改善に貢献できるような世界の実現を目指している国連食糧農業機関(Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO)は、食料と農業は持続可能な開発へのカギであり、SDGsの達成には不可欠であると考え、持続可能で包摂的な農業・農村開発を進め、少ない労働量で多くを生産できるような体制づくりに努めています。
プラン・インターナショナルの取り組み
さまざまな問題が複雑に絡み合い、ときには世代を超えて連鎖すると言われている貧困の撲滅には、多方面からのアプローチが必要です。プラン・インターナショナルは、以下に示す7つの分野に注力し、子どもたち、家族、そして地域全体が貧困の負の連鎖から抜け出すことを目指しています。
1. 質の高い教育
プラン・インターナショナルは、子どもたちに、潜在能力を最大限に発揮するための知識とライフスキルを習得する機会を提供しています。教師へのトレーニング、校舎や衛生設備の建設・修繕を通じ、大勢の子どもたち、特に女の子たちが安全・安心な学習環境で質の高い教育を受けられるよう支援しています。
2. 子どもの成長
貧困を削減するためには、保健医療へのアクセスは不可欠です。プラン・インターナショナルは、活動地域のコミュニティに診療所を建設し、医療従事者へのトレーニング、設備や医薬品を整備・提供することで、子どもたちの健やかな成長を支援しています。
子どもたちの生存に不可欠な水と衛生についても、コミュニティの学校に男女別トイレや給水設備を建設し、住民たちが施設や設備を適切に維持管理できるよう支援しています。
3.性と生殖に関する健康と権利
開発途上国では、性と生殖に関する健康の問題が出産可能年齢の女性や女の子の健康障害や死亡の主な原因になっています。プラン・インターナショナルは、すべての子どもや若者たちには、人生において一切の強制や暴力、差別、虐待を受けることなく、性と生殖の健康に関する十分な情報に基づいて自らの人生を自由に選択する権利があると信じています。そのため、妊産婦のための保健サービスや家族計画などのリプロダクティブ・ヘルスケアに注力し、女の子や女性が自身の健康を守り、出産する子どもの数、時期、出産間隔を調整・選択することを可能にすることで、彼女たちが勉学に励み、仕事をし、そして家族を貧困から救う機会を得ることができるよう支援しています。
4. 生計向上
プラン・インターナショナルは、人々が厳しい経済状況を克服し、収入を増やすためのスキルとレジリエンス(回復力)を備えることができるよう、コミュニティの繁栄に必要な経済的安定を得られるよう支援しています。パートナーやステークホルダーと協力し、人々が生計を立て、家族を支えることができるよう、職業トレーニングや起業支援を実施し、村落貯蓄貸付組合の結成も支援しています。
5. 子どもの参加
プラン・インターナショナルは、子どもたちが自分たちの権利についての学びを深め、地域社会のなかで積極的な役割を果たすことができるよう、すべての活動に子どもたちの参加を促しています。子どもたちが自分の将来を自らの意志で選択し、自分の言葉で意見を表明し、社会活動に参加することで、周囲の大人たちにも影響を与えるような意志決定の場にも関与することができるようになります。
6.緊急支援
世界は今、かつてないほど深刻な食料危機に直面しています。最も飢餓に苦しむ国々では、歩き出す前の幼い子どもたちが1日1食、ときにはそれ以下の食事で生き延びており、空腹で学校に行けない子どもたちがいる地域では教室全体が空っぽになっている学校もあれば、次にいつ何を食べられるか分からない家族も大勢います。
飢餓が最も深刻なホットスポットでは、生き延びるために娘を強制的に結婚させる家庭も増えており、多くの女の子が児童労働やジェンダーに基づく暴力、性的搾取、望まない妊娠の危険にさらされています。このような飢餓問題に苦しんでいる人々、特に自国を離れざるを得ない状況に置かれた難民に必要な物資を届ける短期的な支援を緊急支援と言い、プラン・インターナショナルも数多くの支援活動を実施しています。
取り組みの例
プランは、紛争が激化し多くの子どもたちや家族の命が危険にさらされているスーダンへの緊急支援として、子どもたちとその家族に食料や清潔な水、その他の生活必需品を提供することに重点を置いた活動を実施しました。中長期的には子どもの教育やジェンダーに基づく暴力の防止にも力を入れていく予定です。
活動地域と活動内容
- 北ダルフール州:628世帯以上に食料やその他の必需品を配布し、5つの保健所に物資を提供
- 北コルドファン州:避難民の家族に食料を提供
- 白ナイル州:50世帯にノン・フード・アイテム※を配布
- ※ノンフード・アイテム:物資を配給する支援のうち、食料以外のすべての物資を指し、衣服、調理器具、衛生用品、寝具などが含まれます。

ノン・フード・アイテムを受け取った国内避難民の家族(スーダン)
7.自立支援
プラン・インターナショナルは、「地域の自立」を最終目標に掲げてプラン・スポンサーシップという基幹支援に基づいた活動を展開しています。「与える」「施す」といったサポートではなく、地域住民、特に子どもたちが活動に主体的に関わる、「子どもとともに進める地域開発」を推進することで、最終的には地域全体が自らの力で貧困から脱却し問題を解決できるようになることを目指して活動しています。
自立支援とは、食料事情の改善や、社会基盤の構築・再建を促す支援で、短期的な解決にはつながるものの直接的な解決にはつながりにくい緊急支援とは異なり、中長期的に人々が自立して余裕のある生活を送ることができる基盤を整えることを意味します。

学用品の支給に喜ぶ子どもたち(ナイジェリア)
取り組みの例
プラン・インターナショナルは、2023年6月から、ラオスにおける「女の子の衛生改善」を実施しています。ラオス北部の山岳地域にあるウドムサイ県では、貧困率の高さに加え、安全な水の確保が難しいことが大きな課題となっています。特にラー郡とナモー郡の多くの学校では、子どもたちが安心して使える給水・衛生設備が備わっていません。そのため、子どもたちが快適な学校生活を送れるように、小中学校における給水システムの設置、衛生設備(男女別トイレ、バリアフリートイレ、手洗い場)の建設および修繕、月経衛生管理などに関する生徒によるクラブ活動、教師や政府職員を対象とした衛生改善や月経衛生管理、包括的性教育に関する研修、村落教育開発委員会および保護者を対象とした衛生管理に関する啓発活動などを行う予定です。
プラン・インターナショナルが実施したこと
- 小中学校における給水システムの設置、衛生設備(男女別トイレ、バリアフリートイレ、手洗い場)の建設および修理
- 月経衛生管理に関する子どもの指導
※月経衛生管理とは「月経期間中、安全で衛生的に過ごすこと」を指す - 教師や郡職員を対象とした衛生改善や月経衛生管理、包括的性教育に関する研修
- 村落教育開発委員会および政府関係者を対象とした衛生管理に関する啓発活動
世界から貧困を無くすために私たちができること
ここ数年におよぶコロナ禍の影響で、世界の状況は一変してしまいました。これまで、潜在的に存在しつつも見過ごされてきた問題が可視化され、世界のさまざまな地域でお金がなく経済的に困窮した暮らしを送らざるを得ない大勢の人々の姿が浮き彫りになっています。本来であれば、その国の政府が先頭に立って取り組むべき問題ですが、進捗は遅々としており解決までの道のりは遠いのが現状です。

国内避難民キャンプの女の子たち(ニジェール)
世界に広がっている貧困問題を解決するには、私たち一人ひとりがこの問題を自分事として捉え小さな一歩を踏み出すことが大切です。例えば、支援団体やボランティアが主催するチャリティランなどのイベントに足を運んでみたり、地域の子ども食堂やフードバンクなどの活動に参加してみたりすること、支援業界で信頼を得ている国際NGOや認定NPOへの寄付や募金も、間違いなく問題解決への一歩に繋がるはずです。
そして、世界の貧困問題に関する特集記事を見つけたり、アクションを起こしたりした際には、SNSなどを通じて学校や職場の周りの人にもシェアしてみましょう。周りの人があなたの発信から勇気をもらい活動始めるきっかけとなる可能性だってあります。SDGs目標達成に向けて、世界が一丸となって「貧困撲滅」のために動き出している大きなうねりのなかで、自分にもできる小さな一歩を探してみてはいかがでしょうか。
運営団体
国際NGOプラン・インターナショナルについて
プラン・インターナショナルは、女の子が本来持つ力を引き出すことで地域社会に前向きな変化をもたらし、世界が直面している課題の解決に取り組む国際NGOです。世界75カ国以上で活動。世界規模のネットワークと長年の経験に基づく豊富な知見で、弱い立場に置かれがちな女の子が尊重され、自分の人生を主体的に選択することができる世界の実現に取り組んでいます。

SNSでも情報発信を行っています。
お気軽にフォローしてください
あなたの寄付で、誰かの人生に可能性が生まれる。
公式SNS
世界の子どもたちの今を発信中











