- 国際NGOプラン・インターナショナル 寄付・募金で世界の女の子を支援
- 特集
- おしえて!プラン
- 【おしえて!プラン】「アドボカシー」を分かりやすく解説
【おしえて!プラン】「アドボカシー」を分かりやすく解説
( 更新)
「おしえて!プラン」は、プラン・インターナショナルの活動や報告に出てくる用語をわかりやすく説明するシリーズ記事です。
今回は「アドボカシー」を取り上げます。社会に対して声をあげるアドボカシーは、プランの大切な活動のひとつです。実際に法律を変えた例を交えてご説明します。

Q.アドボカシーとは?
A.社会をよりよくするための「政策の改善」にむけた、提言活動のことです。
世界が抱える問題を解決するためには、政府としての取り組みが必要です。時には法の改正や、新しい法律を作ることが求められる場合もあります。まずはそれらの問題を多くの人に知ってもらい関心を高めること、そして政府に「政策提言」として声を届けること、この一連の活動を「アドボカシー」といいます。最終的に、政策や法律をより良い方向へ変えることを目指します。
- ※アドボカシー(advocacy):「擁護」や「支持をする」などと訳される英語です。社会的に弱い立場にある人たちの権利を守る/主張を代弁するという意味合いで、広く使われています。

プランの活動を応援する
アドボカシーの3つの側面
アドボカシーの活動には、大きく分けて「実態調査」「直接の呼びかけ」「意識啓発」の3つの側面があります。アドボカシーを政策に反映するためには、長い時間がかかります。複合的に活動を行うことが大切です。
実態調査
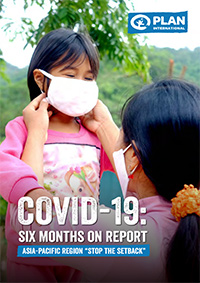
政策を変える必要性や、影響の大きさを明らかにしなくてはなりません。問題に対する独自の調査や、報告書の発表などを通して、その課題を解決する重要性を提起します。
直接の呼びかけ
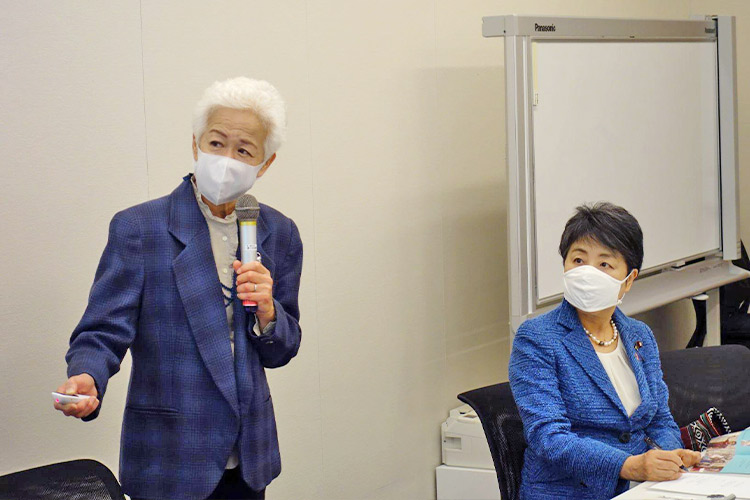
各国政府や国連に対して、政策を変えるよう呼びかけます。国際会議への参加や、文書による提言があります。政治家や省庁との勉強会を行うなど、理解促進のための活動も行います。
意識啓発

キャンペーンや広報活動を通して、人々の意識を高め、行動を喚起するために活動します。問題に対して、多くの人が関心を寄せていることを示し、政策の改善につなげていきます。
多くの人が問題を知り、政策の必要性を理解するためには、
中長期的な視点での活動が必要です。
実際に法律を変えた!~アドボカシーの成果~
プランがアドボカシー活動を通じて実現したい社会は、世界中のあらゆる女の子や若い女性が、自分の未来に希望を持ち、「なりたい自分」を目指せる社会。これまでプランが各国で行ってきた活動が、実際に法改正や政策に結び付いた事例をご紹介します。
プランの活動を応援する
今も世界には、見直さなければならない法律や制度が存在しています
声をあげることで、私たち自身がよりよい社会を
作っていくことができるのです。
グローバルな働きかけで誕生した「国際ガールズ・デー」
「国際ガールズ・デー」は、「女の子の権利」や「女の子のエンパワーメント※」の促進を、広く国際社会に呼びかける日。プランの働きかけを受けて、国連によって定められました。これもアドボカシーの成果です。
プランは2007年から毎年、女の子の現状をまとめた「世界ガールズ・レポート」を発表してきました。これにより世界の関心が集まり、女の子を取り巻く問題の解決にむけた機運が高まりました。
その後も途上国の女の子たちが抱える問題を訴え続けてきたほか、2009年には、カナダのプランが中心となって国際ガールズ・デーの制定にむけた嘆願書を集めました。そして、2011年2月にニューヨークで行われた「国連女性の地位委員会」には、プランの活動地域から12人の女の子が参加して女の子の権利促進を呼びかけるなどの活動を続けた結果、その年の12月に「国際ガールズ・デー」の制定が国連により承認されました。

現在取り組んでいるアドボカシー活動
プランは現在も、女の子・女性のエンパワーメントを促進し、ジェンダー平等を達成するために、さまざまな活動を積極的に展開しています。女の子であるという理由で不当な扱いを受けたり、自分の能力を十分に発揮することができない現状を明らかにしています。
新型コロナウイルス感染症(途上国)
今、世界の女の子たちが苦しんでいるのが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによるさまざまな影響です。 2020年、国連は感染症に起因する教育の混乱で、学校に戻れない女の子は1100万人に上る可能性があると予測
しています。
プランは実態調査やキャンペーンを通じ、女の子への教育が途絶えることのないよう、国際社会に訴えています。
新型コロナウイルス感染症(日本国内)
国内でも新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響は大きく、ジェンダーに基づく暴力や、望まない妊娠に関する相談も増加しています。緊急避妊薬へのアクセス改善を求める要望書を提出したほか、ユース女性を対象に行ったアンケート調査をもとに、経済支援の拡充や、暴力・ハラスメントの予防・対応の強化など、状況を改善するための提言に取り組んでいます。
気候変動
気候変動が世界的に喫緊の課題となるなか、プランは、気候変動による大規模な食料危機や、その影響により中途退学や早すぎる結婚を余儀なくされている⼥の子たちが増加していることを訴えています。さらに、各国のリーダーに対し、温室効果ガス排出削減の⽬標を引き上げ、少なくとも年間1000億ドルを拠出するよう求めています。
生理にまつわる不利益
女の子や若い女性が置かれている現状を可視化することを目的に、イギリス、アメリカに続き、日本でも「生理」を切り口に調査を実施しました。調査結果からは、「生理の貧困」という経済的困窮だけでなく、生理にまつわるスティグマ(恥とみなされること)などのネガティブな感情が、女の子や若い女性の機会損失につながる可能性が明らかになりました。

すべての人が「なりたい自分」を目指せる社会に
プランは、SDGsが目標に掲げる「誰も取り残さない」社会の実現のために活動しています。特に弱い立場に置かれやすい女の子や若い女性、移民、難民、少数民族やセクシュアル・マイノリティ、そして障害のある人たちの権利を守ることが大切です。
これからも取り残されがちな人々の声に耳を傾け、子どもや若者たちとともにアドボカシーを展開していきます。


国際NGOプラン・インターナショナルについて
プラン・インターナショナルは、女の子が本来持つ力を引き出すことで地域社会に前向きな変化をもたらし、世界が直面している課題の解決に取り組む国際NGOです。世界75カ国以上で活動。世界規模のネットワークと長年の経験に基づく豊富な知見で、弱い立場に置かれがちな女の子が尊重され、自分の人生を主体的に選択することができる世界の実現に取り組んでいます。

SNSでも情報発信を行っています。
お気軽にフォローしてください
関連リンク
あなたの寄付で、誰かの人生に可能性が生まれる。
公式SNS
世界の子どもたちの今を発信中

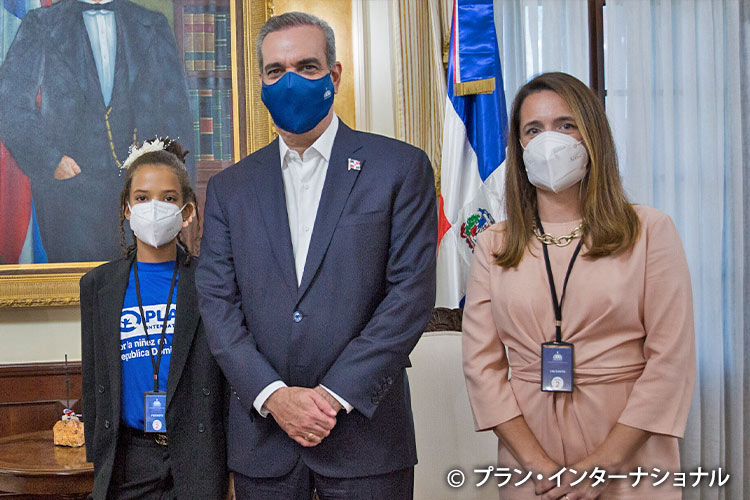





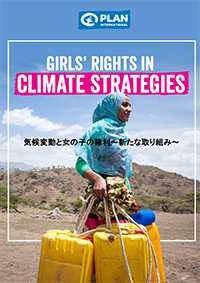









女性性器切除(FGM)が刑事犯罪に(スーダン)
2020年、FGMを刑事犯罪とする刑法の改正が閣僚会議で承認されました。
女性性器切除(FGM)とは、アフリカ・中東・アジアの一部の国々で今も行われている危険な慣習です。プランは2008年からスーダンの全国児童福祉協議会やユニセフと協力し、根絶にむけた話し合いを広げていくキャンペーンを行いました。